
Profile
細川 忍 (ほそかわ しのぶ)
呼吸器内科 副部長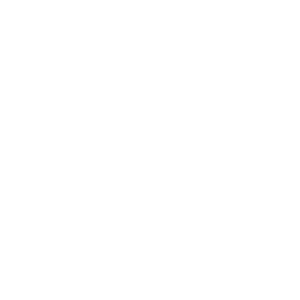
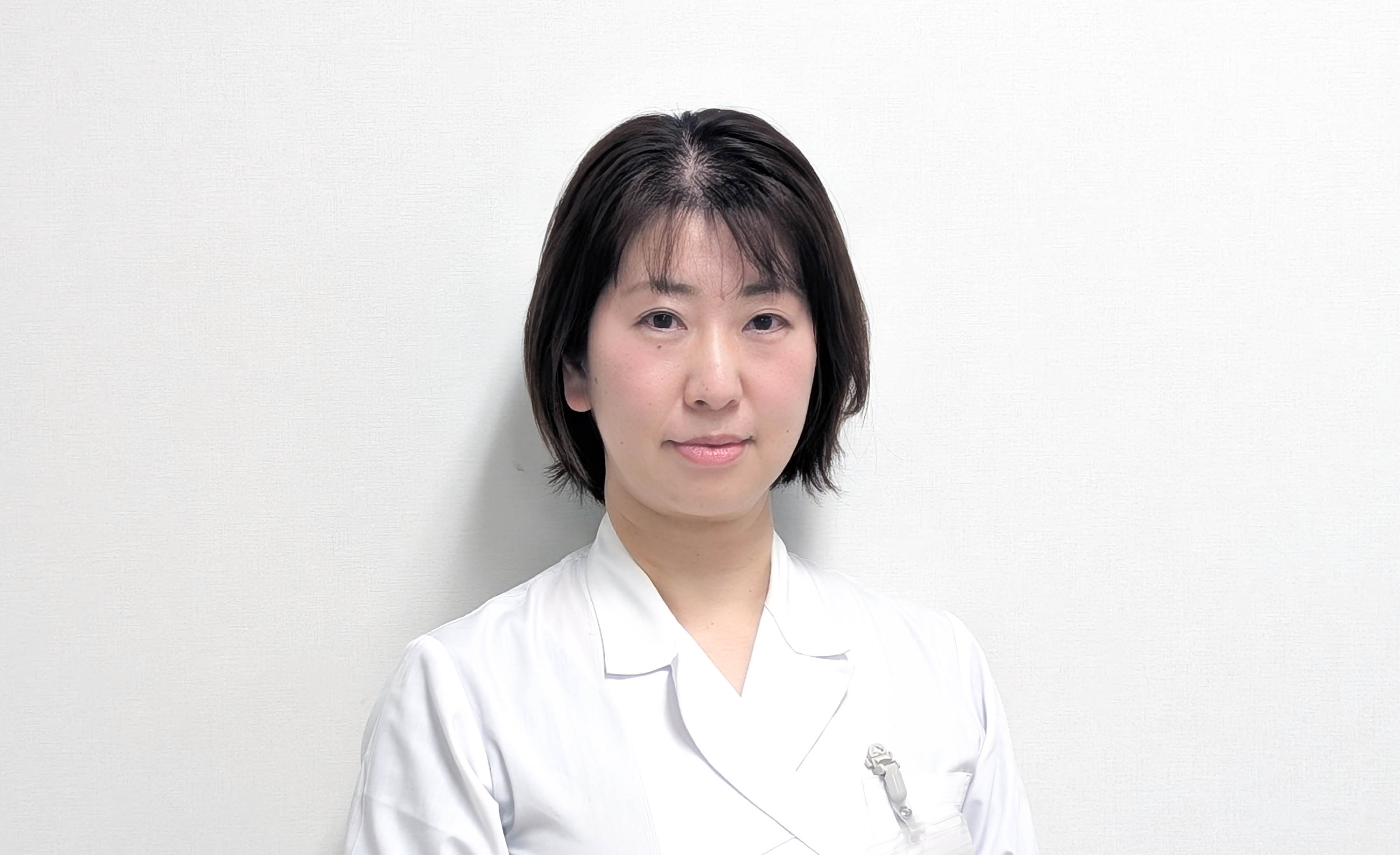
1973年に香川県坂出市で生まれる。1998年に岡山大学を卒業後、岡山大学病院第二内科、十全総合病院、岡山赤十字病院で研修を行う。金田病院内科、国立病院岡山医療センター(現 岡山医療センター)呼吸器内科シニアレジデント、岡山大学病院第二内科医員、岡山大学医学部(血液・腫瘍・呼吸器内科学)研究生を経て、2005年に岡山赤十字病院呼吸器内科に赴任する。2015年に岡山赤十字病院呼吸器内科副部長に就任する。 日本内科学会総合内科専門医、日本呼吸器学会指導医・専門医・代議員、日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医・協議員、日本呼吸器内視鏡学会指導医・専門医・評議員、日本がん治療認定医機構がん治療専門医など。
1987年に岡山県津山市で生まれる。2012年に福井大学を卒業後、岡山医療センターで初期研修を行う。2014年に津山中央病院、2015年に岡山医療センターで後期研修を行う。2017年に岡山大学病院呼吸器・アレルギー内科の医員となる。2019年に岡山大学大学院に入学する。2022年に岡山赤十字病院呼吸器内科に医長として勤務する。2024年に岡山大学大学院を修了する。日本内科学会認定医、日本呼吸器学会専門医、日本呼吸器内視鏡学会専門医など。
1998年に岡山県岡山市で生まれる。2022年に岡山大学を卒業後、岡山赤十字病院で初期研修を行う。
2024年から岡山赤十字病院呼吸器内科で専門研修を行っている。
Contents
- #01岡山赤十字病院
- #02医師を目指す
- #03初期研修で岡山赤十字病院へ
- #04岡山赤十字病院での初期研修
- #05専門を選ぶ
- #06キャリアを積む
- #07救急
- #08今後のビジョン
- #09育児短時間勤務制度
- #10院内保育所
- #11病児保育所
- #12女性医師の会
- #13岡山赤十字病院の福利厚生
- #14寮
- #15ワーク・ライフ・バランス
- #16メッセージ動画
- #17病院紹介
Interview
Section01
#01 岡山赤十字病院
ー 病院の特徴は?
細川当院は、岡山市のみならず、近隣の玉野市、瀬戸内市、備前市などからも患者が受診し、三次救急を担っています。また、当院が市内のほかの病院と大きく異なっているのは日本赤十字社の病院ならではの災害医療に携わっていることです。やはり高度医療、救急医療、災害医療の3つが当院の柱です。当院のような500床前後の規模の病院が岡山市内には多いので、こういった特色を出しつつ頑張っていきたいと思っています。
安東私たちの所属する呼吸器内科の特徴は市中病院でありながら治験や臨床試験を積極的に行っていることです。それから気胸センターを持っているので、難治性の患者さんの紹介をお受けすることが多いです。
ー 初期研修での人気の秘密は?
横出細川先生がおっしゃったように、同程度の規模の病院は岡山市内にいくつかあるのですが、学生的な立場で見ると、当院は三次救急をしていて、救急医療を頑張っている病院だという印象です。そのため、2年間の初期研修で救急を頑張りたいという気持ちを持っている学生に人気の病院になっています。
Section02
#02 医師を目指す
ー 医師を目指したきっかけをお聞かせください。
横出私は父が医師なので、幼少期から身近なところに医師がいたことが進路に影響していたのかなと思います。私が本当に小さい頃で記憶がないのですが、真夜中に家の電話が鳴ったことがあったそうです。夜中だしあえて出ないという可能性もあったと思うのですが、父が「こういう電話には出ないといけない」と言って電話に出たら、ほかの土地で一人暮らしをしている祖母が、倒れて意識朦朧の状態で電話をかけてきていたことが分かりました。そしてすぐに父が救急車を呼んだところ、祖母はくも膜下出血でしたが、何とか生命を取り留めました。おそらく父が電話に出なかったら、祖母は助かっていなかったかもしれません。今も元気に過ごしている祖母を見ると、父を医師として尊敬します。医師は多くの人の健康を守る仕事ですが、多くの人だけでなく、家族のような身の回りの人や自分にとって大切な人の健康を守れることも魅力だなと感じたことなどがあり、私も医師を目指しました。
安東私はそんなに大したエピソードはありません。私は医師が多い家系ではなく、普通の家庭で育ちました。祖父母との3世代同居をしていたのですが、祖母が骨折や何かで何度か入院したことがあり、何か力になりたいなという思いから、医師を目指すようになりました。
細川私も医師家系ではありません。私が小学生の頃は現在のように多くの女性が働いている世の中ではなかったのですが、母から「自立できる仕事をして、自分で生きていけるようになりなさい」と言われていました。ちょうどその頃に大河ドラマの「いのち」が放映され、女性が医師になり、地域医療に携わるというストーリーだったのですが、これを見て医師という仕事を意識しました。そして中学2年生のときに母が人間ドックを受け、胃にポリープが見つかったんですね。医師の言葉の影響は大きいもので、「精密検査をしてください」という言葉を母はがんではないのかと受け止め、かなりナーバスになったんです。結局は良性のポリープでしたが、家族のそのような姿を見たことにも影響を受けました。その精密検査のときに、たまたま私もついていったところ、母が先生に「この子も医師になりたいんです」と言ったからだと思うのですが、内視鏡の検査の様子をレクチャースコープで見せていただきました。現代のようにテレビで医療特集などを取り扱う事もあまりなかったであろう時期に胃の内視鏡検査をライブで見たことが衝撃的で、私も医師を目指して、ここまで進んできました。一つの出来事ではなく、色々な出来事からの流れで医師になろうと決めて、何とかここまでやってこられたというところですね。
ー 学生時代に思い出に残っていることはどのようなことですか。
横出弓道部での活動です。岡山大学の弓道部は80人から90人ほどの部員がいる大所帯で、メンバーと一緒にとても力を入れて頑張っていました。西医体(西日本医科学生総合体育大会)の団体戦で2回優勝できたことが特に思い出に残っています。
Section03
#03 初期研修で岡山赤十字病院へ
ー 初期研修で岡山赤十字病院を選ばれたのはどうしてですか。
横出救急を頑張っている病院ですし、初期研修では色々な疾患に触れて、急性期病院での初期対応をしっかりできるようになりたいと思っていたので、当院を選びました。
Section04
#04 岡山赤十字病院での初期研修
ー 岡山赤十字病院での初期研修はイメージ通りでしたか。
横出概ねイメージ通りでした。私が入職した年はまだコロナ禍で、第7波ぐらいの時期でした。特に最初の1年は救急の患者さんも多かったので、そういう忙しさの中で研修できたことは力になったかなと思っています。
ー 指導医の先生のご指導はいかがでしたか。
横出素晴らしい先生方ばかりでした。呼吸器内科を目指して、初期研修を始めたわけではなかったのですが、初期研修で各科をローテートする中で呼吸器内科にはトータルで3カ月回ったんです。呼吸器内科を回ったときに先生方からとても丁寧なご指導をしてくださったので、呼吸器内科に興味を持てました。今、こういう進路に進んでいますし、大きな影響を受けたと思います。
細川私が研修していた時代とは色々な面で違いがありますので、その違いを意識しつつ指導するようにしています。
安東一緒に診察したり、検査結果をどう解釈するのかなど、そういったことをディスカッションできる機会を設けたり、患者さんへの説明に行ってもらったりなど、一つ一つ確認しながら指導しています。
ー 初期研修を振り返ってみて、いかがでしたか。
横出内科の各診療科が揃っている病院ですので、2年間でほとんど全ての内科を回り、学ぶことができました。指導医の先生が1対1でついてくださって研修する科が多かったので、分からないことなどはその都度、直属の指導医の先生に確認しながら勉強しました。救急だけでなく、内科医になるための初期研修としてもとても充実していたと思います。
Section05
#05 専門を選ぶ
ー 先生方が専門を呼吸器内科に決められた理由をお聞かせください。
横出私は初期研修1年目の4月、5月が呼吸器内科で、呼吸器内科からローテートが始まったんです。これは意図してというわけではなく、同期とローテート順を決めるので、半分ぐらいは偶然です。
そのときは呼吸器内科を志望科としてイメージしていなかったのですが、内科に進みたいという気持ちは漠然とありました。そういった状態で始めたのですが、最初についた指導医の先生がとても丁寧にご指導くださったんですね。医師になって1カ月目で、まだ何も分かっていない私を信用してくださり、患者さんとも積極的に関わらせていただいて、私の意見を「確かにそうだね」と聞いてくださって、診療内容に組み込んでいただくなどの対応をしてくださったことがきっかけで、内科の中でも呼吸器内科に興味を持ちました。呼吸器内科は肺がんや喘息のようなアレルギー疾患、間質性肺炎、感染症などの色々な分野に分かれていきますし、疾患の幅広さを備えた内科だと思いますので、そういった意味でも呼吸器内科に進めば、内科医としての自分の力になるのではないかと考え、呼吸器内科を選びました。
安東私も初期研修を始めた頃は呼吸器内科志望でなく、内科全般で考えていました。私の初期研修先は当院ではありませんが、研修医1年目の最初に呼吸器内科を回ったんです。その呼吸器内科の先生方がとても丁寧に接してくださったことは大きかったですね。また、医師になって1ヶ月たたない時期に平日の日中に患者さんが急変して、「とりあえず行きます」と言ったものの、何もできなかったことがありました。その後、上級医の先生に対応頂き、NPPV装着などして状態は落ち着きましたが、呼吸不全の時など状態悪化時に対応できる医師になりたいと思ったこともきっかけの1つだと思います。その他にも呼吸器内科の先生方から様々なサポートや指導を受けたことで、呼吸器内科を選びました。
細川私は2人とは違う研修システムを経ています。
私の頃は卒業した時点で何科に行くのかを決め、大学のどの医局に所属するかを決める学生が大部分を占めていました。私は全人的に診ることができる科に行きたいということで内科を志望して、岡山大学の第二内科に入局したんです。そして内科医としての研修が始まったのですが、私も最初に指導してくださった先生が呼吸器内科の先生でした。おふたりの話を聞いても、やはり最初の指導医の存在には大きな影響を与えられるものなのですね。
2年目の研修病院であった当院でも呼吸器内科の先生方との出会いがあり、最終的に呼吸器内科を選ぶことになりました。おふたりも言ったように、呼吸器内科は幅広い分野であり、疾患が非常に多岐にわたっており、とても難しいものですし、その難しさから実際の診療は大変な部分もあります。呼吸器疾患の奥深さを興味深く感じてくれる人が呼吸器内科を選ぶ人には多いのではないかと思います。
ー 横出先生が専攻医研修先として、岡山赤十字病院に決めたのはどうしてですか。
横出初期研修で当院の呼吸器内科の先生方に丁寧にご指導いただきましたし、実際に当院の呼吸器内科の先生方の診療を見たことで呼吸器内科に進もうと思いましたので、引き続きこの環境で専攻医になることを決めました。
ー 岡山赤十字病院内科専門医プログラムの特徴をお聞かせください。
横出1年目は当院で、主に志望科を回ります。希望に応じて違う科も回ることができるのですが、多くの人が自分の進む科で1年間の研修をしています。2年目は1年間、外の病院に出ます。私の場合は最初の半年間は県北地域の病院、次の半年間は岡山市内の病院の予定です。3年目にまた当院に戻ってきて、1年目と同じように呼吸器内科を1年間、研修します。
ー 専攻医研修で勉強になっていることはどういったことですか。
横出初期研修では自分が主治医になることはまずなく、指導医の先生について診療するわけですが、専攻医になると自分が主治医となって診療を決めていきます。責任も出てくるので、初期研修のときよりはより一層、身の引き締まる思いで診療しています。
ー 専攻医研修で辛いことはありますか。
横出医学には正解のないことが多いです。教科書を読んでも答えはないですし、全ての患者さんが教科書通りの病状であることもありません。病状でない状況もそれぞれの患者さんによって違いますので、自分と患者さんにとっての正解をどういうふうに見つけていくのかが本当に難しく、難しいという意味で辛いことはよくあります。

研修医の先生と気管支鏡検査の練習をしている風景
ー 今後はどういった専攻医研修を行っていきたいですか。
横出4月からの1年間は外の病院に出て、呼吸器内科以外の内科もローテートして専門研修をする予定です。今年度はほとんど呼吸器内科に従事していましたが、これからの1年はほかの科の勉強をしっかり行い、内科医としての診療能力を高めていきたいと思っています。
ー 岡山赤十字病院に来られた経緯をお聞かせください。
細川最終的には医局人事です。呼吸器内科のシニアレジデントを経験したあとで大学病院に戻りました。研究生として2年ほど研究をさせていただいて、博士号を取得する目途がたち当院に赴任しました。医局人事ではあるのですが、研修医のときに当院で研修したことがあり、呼吸器内科のアクティビティの高さを知っていましたので、「日赤の呼吸器内科に行きたいなあ」というアピールをこっそりしていました(笑)。その後、ご縁があり、赴任することになりました。
安東私も医局人事です。大学院生をしていたのですが、研究にある程度の目処が立ったので、そろそろ外の病院でスタッフになりましょうということで、当院への異動が決まりました。
ー 医師として、影響や刺激を受けた人はいますか。
横出私はまだ医師になって3年目ですので、今、一緒に働かせていただいている呼吸器内科の先生方に日々、影響や刺激を受けています。
安東1人の方を決めることは難しいですね。もちろん初期研修でお世話になった先生方、特に呼吸器内科の先生方には大きな影響や刺激を受けました。その後も色々な病院で研修をしましたし、今もスタッフの先生方、専攻医の先生方を含めて、色々な先生方にお世話になっているので、どなたか1人に決めるのは難しいです。
細川私は2人の方を挙げさせていただきたいです。驚くことに、当院に赴任して20年が経とうとしています。前半の10年にお世話になったのが前の部長の渡辺洋一先生で、後半の10年にお世話になっているのが現在の部長で副院長でもいらっしゃる別所昭宏先生です。
医師になって8年目に当院に赴任し、それから20年を当院で過ごしてきましたが、このお2人には大きな影響を受けました。前部長の渡辺先生には医師としてのベースを作っていただきました。例えば、当院は急性期の忙しい病院なので、多くのことをこなしていかなくてはいけません。そのときに柔軟性や瞬発力を持って働くにはどうしたらいいのかなどですね。そして人間は年をとると自分のやり方が固まっていきます。一方で周りの意見を吸収できなくなる可能性があります。渡辺先生は「周りの意見を常に聞ける人間でいなさい」とよく言ってくださっていました。色々な職種の意見を集約して治療方針を検討するという意味では、すでに20年前から当院の呼吸器内科では多職種連携を取り入れていました。今からすればすごいことですし、その体制は今も続いています。さらに20年前はまだワーク・ライフ・バランスという言葉もなく、そのような中で、渡辺先生はオンオフの区別をつけることの大切さをおっしゃっていました。そのあとの10年は別所先生がキャリアを形成していくうえでの手段や仕事の仕方などを教えてくださいました。肺がん診療にあたっても当院では治験や臨床試験を積極的に行っていますし、そういう土台は別所先生が作られたものなので、これを引き継いでいけるように頑張っているところです。学会活動に関しても、市中病院にいながら評議員や協議委員会などの委員にしていただいて参加できているのは別所先生が引っ張ってくださったお蔭です。
Section06
#06 キャリアを積む
ー 岡山赤十字病院での勤務内容をお聞かせください。
横出月曜日の朝から13時ぐらいまでは外来です。私は外来は週に1日だけです。専攻医特有の勤務内容としては週に1回、午前か午後かのランダムなのですが、救急外来の当番が割り当てられていることです。例えば木曜日の13時から17時までは救急外来で働いていたりします。そういった外来や救急外来の当番がないときには病棟業務をしていることが多いです。

安東呼吸器内科共通のスケジュールとしては火曜日午後に病棟ミーティングがあります。入院している患者さんについてのディスカッションを皆でしましょうというものですね。また火曜日にはチェストカンファレンスもあります。これは放射線科、呼吸器外科、呼吸器内科の医師が集まり、放射線治療や外科治療になる症例についての合同のカンファレンスです。水曜日と金曜日の午後は気管支鏡検査となっています。

細川私たちの仕事内容は曜日によって結構違います。呼吸器内科の1週間という感じで私たち3人のスケジュールをお出ししました。

ー 呼吸器内科の中でのサブスペシャリティはおありですか。
細川私は肺がん診療です。研究も肺がんで行いましたし、今も肺がん治療の臨床試験や治験などに関わらせていただいています。
安東私も細川先生と一緒で、肺がんです。大学院でも肺がんの基礎研究をして、学位を取らせていただきました。
ー 診療方針をお聞かせください。
横出診療をする中で心がけていることはとにかく現場に出て考えることです。患者さんのベッドサイドという点でもそうですが、看護師さんとも電話だけのやり取りではなく、できるだけナースステーションに行って情報を共有したり、リハビリのスタッフの方々とも直接お話しができるようにしています。どうしても忙しかったり、入院患者さんの病棟がばらけていたりすると遠隔や電話で済ませたりしたくなるのですが、ベッドサイドに行くことはもちろん、コメディカルの方々ともできるだけ顔を見てやり取りするように心がけています。
安東治療方針を相談するうえで、どうしても患者さんにお話をするときは理解していただけないこともあるので、画像や検査結果を見ながらできるだけ丁寧にお話しすることを心がけています。そして、一回話しただけでは忘れられたり、理解できていないこともあるので、何度かに分けて繰り返し説明したり、皆さんのお気持ちやご意見に沿いながら治療をしていきたいと思っています。
細川2人が言った通りですね。ベッドサイドだけではなく病棟での患者さんの行動などをなるべく自分の目で確かめるよう心がけています。例えばリハビリでの報告を受けるだけでなく、患者さんが病棟で実際に歩いているところをそっと見守り、「このぐらいできるようになったんだな」と確認したり。ベストな治療を目指すにあたっては常に患者さんの背景を考えていくことがより大切だし、そこが難しいところだと最近は思うようになりました。

ー 岡山赤十字病院で実現したキャリアはどのようなものですか。
安東専門医などは当院に来るまでに取りましたが、当院でも何かを実現できるように着々と努力したいです。
細川専門医や指導医の資格は当院に来て取りました。当院では臨床試験や治験においての施設責任者という形で関わらせていただくことが少しずつ増えてきました。それから病院の中での役割ですね。呼吸器内科の診療だけでなく、色々な委員会に参加しています。例えばクリニカルパスの委員会や化学療法のプロトコル委員会などです。
ー これまでの勤務で印象に残っていることはどんなことですか。
細川私は新型コロナウイルスの診療が強い印象に残っています。社会を大きく変えてしまうような感染症のパンデミックが自分が医師をしている間に来たことは衝撃的でした。それまでの医療とは違いましたし、怖かったのも事実です。その中で自分ができることは何かを考えさせられました。もう一つは去年、能登で経験した災害医療です。赤十字病院で働く中で以前から経験してみたかったことの一つでした。私は行ったのは発災直後ではなく、落ち着きつつある時期ではありましたが、医師として重大な経験でしたし、一生忘れないと思っています。
横出私は些細なことですが、今月で当院を離れ、別の病院に移ると患者さんに伝えると、泣いてくださる患者さんがいらっしゃることです。1年にも満たない関わりだったのに、がっちり握手をして泣いてくださって、「身体に気をつけてくださいね」と私の心配までしてくださる患者さんもいて、私のようにまだまだ未熟な医師であっても、患者さんにとっては主治医であることには変わりはなくて、信頼を寄せてくださったのだなと感じます。私もその信頼に応えなくてはいけないと改めて実感したことが印象に残っています。
ー 細川先生は副部長としてのお仕事はどのようなものがありますか。
細川呼吸器内科のスタッフがうまく回っていけるように、部長の先生のサポートを心がけています。
ー 女性の管理職は多いですか。
細川脳神経外科、皮膚科、産婦人科、耳鼻咽喉科、健診部は女性の部長です。私が大学を卒業したときは同期100人中20人が女性でしたが、私の5つ、6つ上の学年だと女性は10人だったんです。今は女性医師が増えていることを実感しますし、女性でトップになる人も出てきているんだなあと思っています。
ー これまでのキャリアを振り返られて、いかがですか。
細川やりたい仕事をしてこられたなという実感はあります。色々な良い出会いもあったし、やりたい仕事の中には難しいこともありましたが、続けてこられたことは良かったです。これまでは人が引っ張ってくださったところも大きかったのですが、今後は自分がそれをどう切り開き、医師としてのキャリアをどう進んでいくのかを考えるのはこれまで以上に大変です。ハードなミッションになりますが、折れずに挫けずにやっていきたいです。
安東ここ数年は大学院生をしていたので、常勤やスタッフとして働くのは久しぶりです。非常勤ですと患者さんとの関わりはところどころになりますので、当院で入院患者さんと長く関わっていくにあたっては丁寧に接しないといけないなと思っています。今は未熟な部分が多いので、上の先生方に相談させていただきながら、より良い医療ができるように頑張ります。
Section07
#07 救急
ー 岡山赤十字病院の救急はいかがですか。
細川三次救急まで対応する病院で、当直帯や休日の日直帯などは内科医も担当しています。 添付にてご確認ください。したがって、当院の内科で働くということは色々な疾患のファーストタッチや鑑別疾患を挙げることをしていかないといけないので、内科力がとても求められます。内科医は皆、大変な思いをしていますが、それだけ日々のトレーニングになっています。その中で、呼吸器内科では呼吸器の救急疾患をそのまま引き継ぐことが多いので、多種多様な呼吸器疾患を診ることができるのが特徴です。しかも呼吸器内科の特徴として、急性期から慢性期まで幅広く、様々な経験ができていると思います。
ー 当直の回数はどのぐらいですか。
横出専攻医は月に4回です。
安東私は月に2、3回です。
細川当院は50歳までが業務当直で、私は50歳になったので、管理当直をしています。これは病院としての対応などが主体の当直で、回数は月に1、2回です。
ー 当直ではどんなことが勉強になりますか。
横出当直では様々な疾患の対応をします。基本的には私たちのような専攻医1人とそれに一緒についてくれる初期研修医1人の2人体制で救急外来を回しています。入院が必要な患者さんが来られたり、あまりにも忙しすぎて2人では回らないときには上級医の先生を呼んで、入院対応をしていただいたり、外来を手伝っていただいています。当院は三次救急の病院ですし、患者さんの数も多いので、救急外来でするべきことと救急外来でそこまで求める必要はないことを判断してスムーズに運営することも心がけています。でも、まだできないことが多いです(笑)。それから下についてくれる研修医を指導する立場でもあるので、自分ばかりでやってしまうのではなくて、研修医と一緒に考え、その研修医にとってもいい時間になるようにということも気をつけています。
Section08
#08 今後のビジョン
ー 今後のビジョンをお聞かせください。
横出私はまだ色々なことを学習していく学年です。いずれはサブスペシャリティを決めていかなくてはいけないのでしょうが、まだあえて決めずに、様々なことに等しく興味を持って吸収していけたらと思っています。
安東まだまだ学ぶことが多いのですが、当院には肺がんを専門にしていらっしゃる先生、良性疾患を専門にしていらっしゃる先生、どちらもいらっしゃいます。私はまだ学ばせていただける立場なので、自分の症例はもちろんですが、ほかの先生が診られている症例も深く学んでいきたいと思っています。
細川常に最新の治療を提供し、研修医や専攻医を指導していく立場ですので、疾患のアップデートをしたり、勉強は続くものです。もちろん、安東先生のような中堅になってきた先生の力にもなりたいし、皆が呼吸器内科で色々な意味で仕事をうまくできるような科にしていきたいので、マネジメント力をつけていきたいです。そして当院の呼吸器内科が常に上を向いていけるように、私の場合は臨床試験や治験といった分野で専門性を活かしていくことも目標です。
Section09
#09 育児短時間勤務制度
ー 育児短時間勤務制度を使われている先生方はいらっしゃいますか。
2人います。定時は8時30分から17時なのですが、1人は8時30分から16時30分までの週3回勤務で、もう1人は週に2回は8時30分から17時まで、週に1回は8時30分から12時30分までの勤務をしています。
Section10
#10 院内保育所
ー 院内保育所も完備されていますよね。
岡山赤十字病院院内保育園という名称で、病院敷地内にあります。
Section11
#11 病児保育所
ー 病児保育所もありますか。
病院の建物内にあります。
Section12
#12 女性医師の会
ー 女性医師の会のようなものはありますか。
安東病院全体ではないですが、この前、集まりましたね。
細川やりましたね。呼吸器内科の女性医師4人で美味しいものを食べようということで、集まりました。また、これからも美味しいものを食べながら憂さ晴らしをしたり(笑)、仕事の場所ではなかなか話せないようなちょっとしたことを話していけたらいいですね。
Section13
#13 岡山赤十字病院の福利厚生
ー 福利厚生についてはいかがですか。
院友会という互助会には全職員が加入しており、10年以上前までは宿泊を伴う旅行をしていたのですが、参加者が少なくなり、しばらくはホテルでの食事会を行っていました。コロナ禍が明けた2024年度はホテルでの食事会を止めて、初の試みとしてバーベキュービアガーデンを開催したところ、過去のホテル食事会参加人数を上回る職員が参加して、大好評でした。日帰りですが、旅行も復活させ、神戸にステーキを食べに行くという内容で開催したところ、こちらも好評でした。
ー 岡山赤十字病院での女性医師の働きやすさはどのようなところにありますか。
育児短時間勤務や深夜勤務免除などの制度があるところではないでしょうか。
Section14
#14 寮
ー 横出先生は初期研修のときは寮に住んでいらっしゃいましたか。
横出住んでいました。寮は病院敷地内にあり、走れば1分かからないぐらいの距離なので、とても便利でした(笑)。まだ築7、8年ほどの建物なので、中もとても綺麗ですよ。
Section15
#15 ワーク・ライフ・バランス
ー ワーク・ライフ・バランスをどのように心がけていらっしゃいますか。
安東呼吸器内科では夏休みや冬休みを積極的に取るように言われています。日数や回数もきちんと決められていますし、仕事からしっかり離れられる時間を作ってくださっているのだなと思います。
横出私がいたこの1年間は専攻医とスタッフが合わせて7人ほどいて、医師数が比較的多かったこともあり、夏休みや冬休みはもちろん、スポット的な振替休日をいただいても大丈夫なぐらいのスタッフがいたので、どうしても休めない状況がなかったです。
細川当院は夏休みが長く、皆がしっかり取れます。一度に休めば連続11日ですし、2回に分けることもできて、ほとんどの人が2回に分けて取っています。2つに分けると土曜日始まりの9日間が1つと、もう1つは土日に2日の年休をくっつけて4連休にするものです。当科では休みの期間は完全にオフになります。また呼吸器内科の特徴として、冬休みがあります。1月から3月にかけて、平日の年休2日と土日をあわせて休みを取れるので、とても楽しみです(笑)。私たちは日頃の週末の休みを完全にオフにすることがなかなかできませんでした。そこで、呼吸器内科では月に1回ぐらいは土日を完全オフにしようという試みを始めました。これは今後の課題だと思います。
ー ご趣味など、プライベートについて、お聞かせください。
細川ベタなのですが、旅行です。コロナ禍になる前の10年間は夏休みに海外に行っていました。私が行きたい場所は皆とずれているらしく、危ないところには行かない安全第一なのが絶対条件ではありますが、初めての海外一人旅はチェコでした。
安東どうしてチェコなんですか。
細川その年の最初に学会でハンガリーに行って、中欧がいいなと思ったんです。それで夏休みの1週間ぐらい前に思い立って準備して行きました。それからはクロアチア、ルクセンブルク、イタリアのアマルフィ、ポルトガルといった変化球なところに行っています(笑)。
安東ベタじゃないですね(笑)。
細川途中からはそういう私を見た母が「私も行きたい」と呟いたので、後半5年は母と出かけてきました。母と一緒の旅行先は割とベタなところを選んでいました。それで10年ぐらい楽しんだあとでコロナ禍になったので、そこで一旦終わりました。ただ、コロナ禍が明けても円安や国際情勢などで海外旅行へのハードルが高くなってしまったことと、年齢を重ねて体力に自信がなくなったので、今度は日本国内の面白いところを見つけるようにしています。去年の夏は下田に行き、開港の地を見てきました。人には「なぜ下田」と言われましたけどね(笑)。
安東私は甘いものを食べることが趣味です。美味しいケーキやクッキーといった洋菓子のお店のリサーチをよくしています(笑)。
細川確かに、いつも机の上にクッキーがありますね。美味しそうだなと思って、見ています(笑)。
安東岡山はフルーツも美味しいですし、甘いものを活力にして頑張っています。
横出私も夏休みや長いお休みは旅行に行ったりしますし、小さい趣味としてはギターです。つい最近も病棟の新年会などで楽器ができる先生方や看護師さんたちと一緒に演奏したという楽しみもありました。
ー 座右の銘などはありますか。
横出私は「初心忘るべからず」を心に刻んでいます。もちろん、まだ初心者なのですが(笑)。とは言え、慣れてきた時期が一番危険だし、何となく経験則的にやってしまうので、常に初心に立ち返って、一つ一つをきちんと調べたり、分からないことは上の先生にしっかり質問して確認したりなど、そういった気持ちを忘れずにやっていきたいです。
細川先ほども言ったように、常に吸収する力をいつまでも持ち続けていきたいことと、この年になったらやはり「健康第一」も大事にしていきたいです。
Movie
Hospital introduction

概要
| 名称 | 岡山赤十字病院 |
|---|---|
| 所在地 | 〒700-8607 岡山県岡山市北区青江二丁目1番1号 |
| 電話番号 | TEL:086-222-8811(代表) FAX:086-222-8841 |
| 開設年月 | 1927年5月 |
| 院長 | 實金 健(みかね たけし) |
| 休診日 | 土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日) 創立記念日(5月28日)※但し、救急外来は除きます |
| 病床数 | 500床 |
| 入院患者数 | 384.6人/日(延べ) (2024年度) |
診療体制
診療科目・部門
総合内科、血液内科、糖尿病・内分泌内科、膠原病・リウマチ内科、腎臓内科、消化器内科、肝臓内科、呼吸器内科、循環器内科、脳神経内科、緩和ケア科、脳卒中科、精神神経科、小児科、外科、消化器外科、呼吸器外科、乳腺・内分泌外科、心臓血管外科、整形外科、脳神経外科、脳血管内治療外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、形成外科、放射線科、麻酔科、ペインクリニック科、歯科、救急部、病理診断
基本診療料
- 初診料(歯科)の注1に掲げる基準
- 歯科外来診療医療安全体制加算1
- 歯科外来診療感染対策加算1
- 初診料(医科)の注16に掲げる医療DX推進体制整備加算2
- 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1)
- 急性期充実体制加算2
- 救急医療管理加算
- 超急性期脳卒中加算
- 診療録管理体制加算1
- 医師事務作業補助体制加算1(15対1補助体制加算)
- 急性期看護補助体制加算(25対1補助体制加算(5割以上))(夜間100対1急性期看護補助体制加算)(夜間看護体制加算)(看護補助体制充実加算)
- 看護職員夜間12対1配置加算1
- 療養環境加算
- 重症者等療養環境特別加算
- 無菌治療室管理加算2
- 緩和ケア診療加算
- 栄養サポートチーム加算
- 医療安全対策加算1(医療安全対策地域連携加算1)
- 感染対策向上加算1(指導強化加算)(抗菌薬適正使用体制加算)
- 患者サポート体制充実加算
- 重症患者初期支援充実加算
- 報告書管理体制加算
- 褥瘡ハイリスク患者ケア加算
- ハイリスク妊娠管理加算
- ハイリスク分娩管理加算
- 術後疼痛管理チーム加算
- 後発医薬品使用体制加算1
- バイオ後続品使用体制加算
- 病棟薬剤業務実施加算1
- 病棟薬剤業務実施加算2
- データ提出加算2
- 入退院支援加算1(地域連携診療計画加算)(入院時支援加算)(総合機能評価加算)
- 認知症ケア加算1
- せん妄ハイリスク患者ケア加算
- 精神疾患診療体制加算
- 排尿自立支援加算
- 地域医療体制確保加算
- 特定集中治療室管理料6(早期離床・リハビリテーション加算)
- ハイケアユニット入院医療管理料1
- 新生児特定集中治療室管理料2
- 小児入院医療管理料3(注2に規定する加算(ア 保育士1名の場合))(養育支援体制加算)
- 緩和ケア病棟入院料1
特掲診療料
- ウイルス疾患指導料
- 外来栄養食事指導料の注2
- 心臓ペースメーカー指導管理料の注5に掲げる遠隔モニタリング加算
- 糖尿病合併症管理料
- 小児運動器疾患指導管理料
- がん性疼痛緩和指導管理料
- がん患者指導管理料イ・ロ・ハ・二
- 外来緩和ケア管理料
- 糖尿病透析予防指導管理料
- 乳腺炎重症化予防・ケア指導料
- 婦人科特定疾患指導管理料
- 二次性骨折予防指導管理料1・3
- 下肢創傷処置管理料
- 地域連携小児夜間・休日診療料2
- 院内トリアージ実施料
- 外来腫瘍化学療法診療料1
- 連携充実加算
- ニコチン依存症管理料
- 療養・就労両立支援指導料の注3に掲げる相談支援加算
- 開放型病院共同指導料
- ハイリスク妊産婦共同管理料(I)
- がん治療連携計画策定料
- 肝炎インターフェロン治療計画料
- 外来排尿自立指導料
- ハイリスク妊産婦連携指導料1
- 薬剤管理指導料
- 検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料
- 医療機器安全管理料1・2
- 救急患者連携搬送料
- 在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料
- 在宅患者訪問看護・指導料の注15(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む)に掲げる訪問看護・指導体制充実加算
- 在宅患者訪問看護・指導料の注16(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む)に規定する専門管理加算
- 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に掲げる遠隔モニタリング加算
- 在宅腫瘍治療電場療法指導管理料
- 持続血糖測定器及び皮下連続式グルコース測定
- 遺伝学的検査
- 骨髄微小残存病変量測定
- BRCA1/2遺伝子検査(腫瘍細胞を検体とするもの)(血液を検体とするもの)
- がんゲノムプロファイリング検査
- 先天性代謝異常症検査
- HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)
- ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-Cov-2核酸検出を含まないもの)
- ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(髄液)
- 検体検査管理加算(IV)
- 遺伝カウンセリング加算
- 心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算
- 胎児心エコー法
- 時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト
- ヘッドアップティルト試験
- 神経学的検査
- 全視野精密網膜電図
- ロービジョン検査判断料
- コンタクトレンズ検査料1
- 小児食物アレルギー負荷検査
- 内服・点滴誘発試験
- 前立腺針生検法(MRI撮影及び超音波検査融合画像によるもの
- 画像診断管理加算1
- 画像診断管理加算3
- 遠隔画像診断
- CT撮影及びMRI撮影
- 冠動脈CT撮影加算
- 血流量比コンピューター断層診断
- 心臓MRI撮影加算
- 乳房MRI撮影加算
- 頭部MRI撮影加算
- 全身MRI撮影加算
- 抗悪性腫瘍剤処方管理加算
- 外来化学療法加算1
- 無菌製剤処理料
- 心大血管疾患リハビリテーション料(I)(初期加算)
- 脳血管疾患等リハビリテーション料(I)(初期加算)
- 歯科口腔リハビリテーション料2
- 運動器リハビリテーション料(I)(初期加算)
- 呼吸器リハビリテーション料(I)(初期加算)
- 摂食機能療法の注3に既定する摂食嚥下機能回復体制加算2
- がん患者リハビリテーション料
- 医科点数表第2章第9部処置の通則5に掲げる処置の休日加算1
- 医科点数表第2章第9部処置の通則5に掲げる処置の時間外加算1
- 医科点数表第2章第9部処置の通則5に掲げる処置の深夜加算1
- 人工腎臓 導入期加算1 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算
- ストーマ処置の注4に掲げるストーマ合併症加算
- 磁気による膀胱等刺激法
- CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー(歯科)
- 組織拡張器による再建手術(乳房(再建手術)の場合に限る)
- 緊急整復固定加算及び緊急挿入加算
- 骨移植術(軟骨移植術を含む。)(同種骨移植(非生体)(同種骨移植(特殊なものに限る。)))
- 骨移植術(軟骨移植術を含む。)(自家培養軟骨移植術に限る。)
- 後縦靭帯骨化症手術(前方進入によるもの)
- 緊急穿頭血腫除去術
- 癒着性脊髄くも膜炎手術(脊髄くも膜剥離操作を行うもの)
- 脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術
- 仙骨神経刺激装置植込術・交換術
- 緑内障手術(流出路再建術(眼内法)及び水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術)
- 緑内障手術(濾過法再建術(needle法))
- 鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む)
- 鏡視下喉頭悪性腫瘍手術
- 乳がんセンチネルリンパ節加算1及びセンチネルリンパ節生検(併用)
- 乳がんセンチネルリンパ節加算2及びセンチネルリンパ節生検(単独)
- 乳腺悪性腫瘍手術(乳輪温存乳房切除術(腋窩郭清を伴わないもの)及び乳輪温存乳房切除術(腋窩郭清を伴うもの))
- ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後)
- 椎間板内酵素注入療法
- 食道縫合術(穿孔、損傷)(内視鏡によるもの)、内視鏡下胃、十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術、胃瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、小腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、結腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、腎(腎盂)腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、尿管腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、膀胱腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)及び腟腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)
- 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)
- ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術(リードレスペースメーカーを含む)
- 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)
- 経皮的下肢動脈形成術
- 骨盤内悪性腫瘍及び腹腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法
- 内視鏡的逆流防止粘膜切除術
- 腹腔鏡下胃切除術(単純切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合))及び腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの))
- 腹腔鏡下噴門側胃切除術(単純切除術(内視鏡手術支援機器を用いる場合))及び腹腔鏡下噴門側胃切除術(悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの))
- 腹腔鏡下胃全摘術(単純切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合))及び腹腔鏡下胃全摘術(悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの))
- バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術
- 腹腔鏡下胆嚢悪性腫瘍手術(胆嚢床切除を行うもの)
- 腹腔鏡下肝切除術
- 腹腔鏡下膵腫瘍摘出術
- 腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術
- 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
- 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術
- 内視鏡的小腸ポリープ切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
- 腹腔鏡下直腸切除・切断術(切除術、低位前方切除術及び切断術に限る)(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
- 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術
- 人工尿道括約筋植込・置換術
- 膀胱頸部形成術(膀胱頸部吊上術以外)埋没陰茎手術及び陰嚢水腫手術(鼠径部切開によるもの)
- 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術
- 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)
- 腹腔鏡下仙骨膣固定術
- 腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術
- 医科点数表第2章第10部手術の通則12に掲げる手術の休日加算1
- 医科点数表第2章第10部手術の通則12に掲げる手術の時間外加算1
- 医科点数表第2章第10部手術の通則12に掲げる手術の深夜加算1
- 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む)(医科点数表第2章第10部手術の通則16に掲げる手術)
- 乳房切除術(遺伝性乳癌卵巣癌症候群の患者に対して行うものに限。)(医科点数表第2章第10部手術の通則19に掲げる手術)
- 医科点数表第2章第10部手術の通則20に掲げる周術期栄養管理実施加算
- 輸血管理料I
- 輸血適正使用加算
- 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算
- 胃瘻造設時嚥下機能評価加算
- レーザー機器加算
- 麻酔管理料(I)
- 麻酔管理料(II)
- 麻酔管理料(I)及び(II)の注5に掲げる周術期薬剤管理加算
- 放射線治療専任加算
- 外来放射線治療加算
- 高エネルギー放射線治療
- 1回線量増加加算
- 強度変調放射線治療(IMRT)
- 強度変調放射線治療(IMRT)の1回線量増加加算(前立腺照射)
- 画像誘導放射線治療加算(IGRT)
- 体外照射呼吸性移動対策加算
- 定位放射線治療
- 定位放射線治療呼吸性移動対策加算
- 病理診断管理加算2
- 悪性腫瘍病理組織標本加算
- クラウン・ブリッジ維持管理料
- 看護職員処遇改善評価料71
- 外来・在宅ベースアップ評価料I
- 入院ベースアップ評価料85
- 歯科外来・在宅ベースアップ評価料I











