内科専門医向け J-OSLER 「J-OSLER攻略!?効率UPと差替え回避の秘訣」
2025 年 9 ⽉ 16 ⽇

⾃⼰紹介・あいさつ
こんにちは、相川よしたけと申します。僕は 2020 年 4 ⽉に内科専攻医となり、3 年間で無事に J Osler を修了することができ、2023 年に内科専⾨医となりました。J Osler の3期⽣です。
J Osler に関して思い出すと、専攻医 1 年⽬は 2020 年の COVID-19 の緊急事態宣⾔の年で、まだワクチンが存在しない世界で内科医の下っ端として院内のコロナ対応に忙殺される⽇々でした。専攻医 2 年⽬になってようやく J Osler の症例登録や病歴要約に取り掛かったものの、ルールが複雑でどう取り組んでいいか分からず、相談できる⼈もいない中、⼿探りで進めていました。今になって思うと、ルールを知らないために多くの時間を無駄にしていたものです。
⾃分も⼤いに J Osler には苦労したため、せめて情報不⾜に悩む⼈が多い現状を変えたいと思い、僕は専攻医3年⽬のときから X で J Osler に関する発信を始めました。フォロワーの⽅からの DM 相談にはすべてお答えし、J Osler に関する既存の発信はすべて読みました。2024 年 7 ⽉に内科学会から新しくリリースされた「病歴要約サンプル」などの資料も踏まえて、発信内容はブラッシュアップしています。
「⽇々の臨床が忙しくて J Osler に取り組む時間がない」
「要領よく J Osler を進める同期と⽐べて焦ってしまう」
「先輩が差替えされたと聞き不安になる」
そんな内科専攻医の皆さんが抱える悩みはよく分かります。
この度、株式会社リンクスタッフ様より e-resident への記事執筆のご依頼をいただきました。J Osler に関する情報はまだまだ少なく、実情が伝わっていない部分もあるかと思います。ここでは、内科専攻医として多忙な臨床現場で戦いながら J Osler と向き合っている先⽣⽅に、「効率よく J Osler を突破するための概要と⼼構え」を書かせていただきます。
総論
J Osler に関しては実に多くの資料があります。J Osler 画⾯右上にある「マニュアル」、⽇本内科学会「プログラム整備基準」、J Osler のホームページ、「研修⼿帳」や⽇本内科学会のホームページ。さらに、「J Osler 病歴要約 作成の⼿引き」「J Osler 病歴要約 評価の⼿引き」「J Osler 病歴要約 サンプル」という資料も公表されています。では、これらの資料を全部読めばルールを理解できて、J Osler を難なく突破できるのでしょうか?
これができないんです。最も新しい資料である「⼿引き」と「サンプル」は分かりやすいものになっていますが、それ以外の資料には J Osler を進める上では関係のない規則も記載されており、情報が分散しています。統⼀した理解は不可能です。なぜか記載されていないルールもあり、こうした未公開のルールを知らないだけでも、容赦なく差替え(病歴要約の新規作成)となる可能性があるのです。
資料としては「J Osler 病歴要約 作成の⼿引き」と「評価の⼿引き」だけを読みましょう。これだけで全てのルールが分かるわけではないのですが、他の資料は出来が悪すぎて読むのも時間の無駄です。古い公式資料ではなく、新しいナマの情報に触れてください。
世代の把握
複雑な J Osler に取り組む上で⼤前提があります。それは⾃分の学年と J Osler 世代の把握です。2025 年 7 ⽉現在、内科専攻医 3 年⽬の先⽣は J Osler 6 期⽣、内科専攻医 2 年⽬以下の先⽣は J Osler 7 期⽣以下ということになりますが、J Osler 7 期⽣以下では症例登録のルールが変わってきます。⾃分の J Osler 世代を確認してからルールを理解するようにしてください。
チェックリスト
⾃分の世代の他にも、J Osler を進めるうえで重要な情報があります。⾃分がこれからローテートする診療科はもちろん、外病院に⾏く期間とその間に研修する診療科はできるだけ早く把握しましょう。当直の頻度や回数も気になるところですが、そこでどのような疾患に遭遇しやすいのかも J Osler には⼤事です。3 年間の間に回る診療科と当直で経験する症例が、J Osler に登録して病歴要約を作る源になっていきます。それによって、経験しにくい領域も出てくるので、症例登録のやり⽅も変わってくるかもしれません。
以上のように⾃分⾃⾝を理解したら、次は指導医のことを知りましょう。病歴要約を作成すると、合計 4 ⼈の指導医が登場することになります。個別指導医、病歴指導医、統括責任者、そして外部査読委員です。このうち最後の査読委員は J Osler のシステムによって割り当てられます。内科専攻医からは査読委員がどこの誰なのか知る由はありません。しかし、個別指導医、病歴指導医、そして統括責任者は内科専攻医が所属する内科専⾨研修プログラムの誰かということになります。病歴指導医についてはプログラムによって決められるため、⼈によってはまだ決まっていない可能性もありますが、統括責任者と個別指導医は調べれば分かると思います。
少し⼤事なことですが、彼ら指導医の専⾨には注意しましょう。統括責任者がどこまで病歴要約の指導に関わってくるかはプログラム次第なのですが、専⾨研修プログラムの責任者になるような先⽣は元教授であったり、⾃⾝の専⾨分野においては著名⼈であることが多いです。そんな先⽣に専⾨分野に関する病歴要約を作って持っていったらどうなるでしょうか?ときに異常に評価が厳しくなることがあるんです。もちろん、時間に余裕があれば、その分野に詳しい先⽣に指導してもらうという積極的姿勢もすばらしいと思います。ですが余裕がなくて指導医の専⾨分野の評価が厳しい環境ということであれば、できるだけ評価が厳しい分野の病歴要約を作らないという戦略も⼤事になることがあります。
⾃分が置かれた環境を理解して、うまく⽴ち回るようにしましょう。
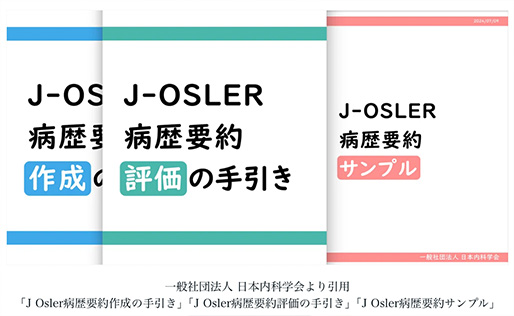
⽤語
J Osler にはいくつかの⽤語があります。もちろん医学⽤語ほどではないですが、J Osler独⾃の概念もあり、ちゃんと理解していないと「差替え」の原因になったりするので、ここで覚えておきましょう。
まずは「差替え」です。これは J Osler おいて最も避けたい事態であり、病歴要約を新たに作成し直さないといけなくなります。この差替えのリスクをできるだけ下げて J Oslerを完了しようというのが、僕の発信の⽬的でもあります。
似たような⾔葉に「要修正」があります。これは、病歴要約⾃体を新規作成する必要なないものの、内容の修正を要求されます。抗菌薬の単位を追記する簡単なものから、考察の書き直しまで⾯倒なものまであります。別に新たに病歴要約を作成する必要はないので、この要修正をそこまで恐れる必要はないと思います。ちなみに、実際には要修正であるにも関わらず、差替えと誤って⾔っている先輩やツイートが散⾒されるため、よく確認して恐れすぎないようにしましょう。
最後に「疾患群」をご紹介します。これは J Osler に独特の概念です。症例登録、病歴要約いずれにも重要なのですが、かつての僕も含めて、ここでつまづく⼈が多いです。「領域」というのが、呼吸器とか循環器、外科紹介といった⼤分類であるのに対して、「疾患群」とは呼吸不全とか ARDS などの領域の下位分類になります。疾患群をカリキュラム通りに網羅しないと⾏けないのですが、⾃分がどれくらい疾患群を制覇できているかは、JOsler システム上の「モニタリング」を使いましょう。
なぜここまで疾患群が重要かというと、疾患群を意識せずに病歴要約を作り「疾患群が重複」した場合、せっかく作った病歴要約が無意味になるからです。例えば、⾎液の病歴要約は 2 つ作成しないといけないのですが、2 つの病歴要約は異なる疾患群から作成しないといけません。同じ疾患群に属する病気(悪性リンパ腫と⾻髄異形成症候群など)から病歴要約を作成してしまうと⽚⽅は無効になるのです。
これらの⽤語、特に疾患群を理解することが J Osler をクリアする第⼀歩です。
症例登録
J Osler で最初に取り組むのが症例登録です。症例を経験したことを登録するだけなら、患者の年齢、性別と病名だけでいいと思うのですが、J Osler では概略と⾃⼰省察を書かないといけません。
内科専攻医 3 年⽬(J Osler 6 期⽣)は全部で 160 症例、内科専攻医 2 年⽬以下には新ルールが適応されて、全部で 120 症例にな
りました。いずれの世代でも疾患群を幅広く登録する必要があります。
J Osler の本丸は、症例登録ではなく病歴要約にあります。症例登録で時間をかけてしまうと予後不良です。症例登録は院内の指導医 1 ⼈に承認してもらえれば完了なので、できるだけ指導医とコミュニケーションを取り、J Osler の実情を理解してもらいましょう。さらに、承認登録の概略と⾃⼰省察には⽂字数の制限はありません。軽く 1 ⾏だけ書けばいいと公式資料にも明⾔されています。複数の診療科をローテートするうちに、承認が早い⼈、レスポンスが遅い⼈、必要以上に評価が厳しい⼈などいるでしょう。承認してもらえれば指導医は誰でもいいので、症例登録では考察は軽く書いて、量をこなしてください。
病歴要約
病歴要約については学年によるルールの違いはありません。A4 ⽤紙 2 枚分の分量で 29 個作成していく J Osler の難所です。
症例登録と同じく疾患群の縛りに気をつけましょう。とにかく 4 ⼈の指導医に評価を受けなければならず、その時々の指導⽅針に左右されがちです。⼊院後経過と総合考察を書いていくわけですが、内科学会の理念としては、内科専攻医の⼈間性と患者との関わりも病歴要約を通じて評価するということになっています。ですので、総合考察では病気のことだけではなく、いかにも⾃分は患者思いでその⽣活背景にまで思いを馳せ、コメディカルと密に連携しながら退院(あるいは看取り)に導いたことをアピールしましょう。
差替えを防ぐコツ
J Osler をストレスなく進めるには、とにかく差替えを防ぐのが⼤事です。最終的には指導医や査読委員が差替えの決定権を持つわけですが、内科専攻医側でもそのリスクを下げることはできます。これまでに書いたことの繰り返しになることもありますが、⼤事なことと思ってもう⼀度聞いて下さい。
指導医の専⾨と疾患群をちゃんと理解しましょう。院内の評価で指導医の要求が⾼くなる分野で病歴要約を提出するのは、やはり悪⼿です。また、疾患群の重複は確実に病歴要約を作り直すハメになるので、ここだけは間違えないようにしましょう。
病歴要約の各論でいうと、消化器のルールが少し複雑です。消化器の病歴要約 3 つは「消化管」「胆膵」「肝臓」から 1 つずつ作成しないといけません。間違って消化管から 2つ作ったりしないようにしてください。さらに、消化器には「腹腔・腹壁疾患」と「急性腹症」に分類されている病気があります。ここからは消化器の病歴要約は作ることができません。⾮常にややこしいですが、ここに分類される病気は外科紹介と剖検症例に使⽤するためにあります。
次に、⾎液の「出⾎性貧⾎」や「鉄⽋乏性貧⾎」にも注意です。⼀⾒すると消化管潰瘍や消化器癌により貧⾎に⾄った症例を、貧⾎として⾎液の病歴要約に使えそうです。しかし、これはかなり差替えのリスクが⾼いです。例えば、消化器癌から鉄⽋乏性貧⾎に⾄った症例を⾎液の病歴要約として提出すると、「これは⾎液ではなく消化器の病歴要約として提出するべきだ」という理由で差替えになる可能性があるんです。「病歴要約サンプル」などの内科学会の資料には、こうしたケースでは考察の内容が該当の病歴要約としてふさわしければいい(貧⾎の場合、考察が消化器癌ではなく⾎液がメインとなっていればいい)というように書かれています。しかしながら、「⾎液の考察としてふさわしい」という明確な基準など存在しません。結局、指導医や査読委員のさじ加減に過ぎないのです。もちろん、運が良ければ差替えされずに突破できますが、これを読んでいる先⽣⽅にはできるだけ運に依存しない⽅法をとってほしいと思います。
まとめ(メッセージ)
最後まで読んでいただきありがとうございます。
すでに内科専攻医として勤務している皆さんにとっては、この記事を読んでますます JOsler が嫌なものになったかもしれません。普段の臨床だけで⼗分に多忙でストレスに晒されますし、J Osler に要求される⼤量の⽂書作成作業を忠実にこなしても、正直⾔って臨床能⼒や専⾨医取得後のスキルには役に⽴たないのが実⽤です。J Osler を進めていこうというモチベーションを維持するほうが難しいと思います。僕もそうでした。
それでも、J Osler 制度が始まってから多くの⼈が病歴要約を書いて、ときに理不尽な⽬に遭いながらも無事に専⾨医を取得してきました。少しずつ先⼈の経験が集積されていい情報にアクセスできるようになっています。僕の発信やこの記事もその 1 つであれば嬉しいです。
J Osler は事務処理能⼒を試すパソコン作業です。臨床能⼒ではありません。割り切りましょう。⾔い⽅を変えれば、この制度を突破するのに特別な才能や体⼒はいらないんです。⼿術の⼿技を練習したり、筆頭著者として論⽂を書く必要もありません。
何があっても気楽にとらえて、早く専⾨医試験の勉強という次のステージに進みましょう。内科専⾨医となった後、先⽣のことを多くの患者さんやスタッフが待っています。どんな医療機関でも内科医が求められています。内科専⾨医になれば、かなり⾃由に働き⽅を選べるようになります。
内科専⾨医として先⽣にお会いできる⽇を楽しみにしています。

