初期研修医向け J-Osler 「内科研修に進むなら知っておくべき"J-OSLER"」
2025 年 9 ⽉ 16 ⽇

⾃⼰紹介・あいさつ
はじめまして、相川よしたけと申します。僕は 2020 年に福島県の病院で初期研修を終了し、内科専攻医となりました。「J Osler」という新しい内科専⾨研修プログラムを経て、2023 年に内科専⾨医となりました。J Osler の3期⽣です。
僕は初期研修を終えてもう 5 年経ちますが、あの濃密な⽇々は医師としても、⼈⽣においても僕にとっていい思い出であり、今に⽣きる糧となっています。僕⾃⾝は同期のなかでは全く優秀な研修医ではなかったですし、当直業務や厳しい外科や⿇酔科のローテートでも遅れをとってばかりでした。忙しい当直の合間、深夜 3 時くらいに薄暗い病院の⾷堂で冷たい⼣⾷を半泣きで⾷べたことは今でも鮮明に覚えています。
これをご覧になっている研修医の先⽣⽅も、⾃分の⾮⼒さや無⼒さにときに愕然としながらも、多くのことを学び医師として成⻑されていることと思います。また、医師 3 年⽬以降の専⾨科や進路を決めていくのも研修医の⼤きな決断でしょう。
僕⾃⾝は外科に興味があり初期研修を始めたのですが、途中で内科志望に切り替えることになりました。研修医のときには知らなかったのですが、内科専攻医になると J Osler というプログラムのもとで多くのレポートを提出しなければなりません。
「内科に興味はあるけど、J Osler の評判が悪いのが不安」
「実際、どれほど J Osler って⼤変なの?」
「内科に進むと決めているけど、研修医のうちに何をすればいい?」
内科に進むことを考えたことのある研修医の先⽣⽅は、⼀度はこのような疑問をもったことがあると思います。
僕は専攻医3年⽬のときから X で J Osler に関する発信を始め、既存の資料や発信を全てチェックしながら、フォロワーの⽅からの DM 相談にはすべてお答えしてきました。内科学会から公開される新しい資料などの情報も踏まえて、X や note、YouTube で発信を続けています。
この度、株式会社リンクスタッフ様より e-resident への記事執筆のご依頼をいただきました。J Osler に関して接する情報は否定的なものが多く、研修医の皆さんには間違った形で伝わっているかもしれません。せっかく内科に興味を持ってくれているのに、J Osler に対して必要以上のプレッシャーを感じて内科を選ばないとするなら、⾮常にもったいないことです。そこでこの記事では、J Osler に関しては多くの知⾒を持つ⽴場から、初期研修医の先⽣⽅に J Osler の正しい実情をお伝えしたいと思います。
J Osler とは
そもそも「J Osler」とはなんでしょうか。⽇本内科学会によると「内科専⾨研修の標準化を図るため、オンラインで研修実績の登録と評価ができるシステム」であり、Online systemfor Standardized Log of Evaluation and Registration of specialty training System から名付けられたそうです(⽇本内科学会, https://www.naika.or.jp/nintei/j-osler/about/)。カナダの医師でジョン・ホプキンス⼤学の名物教授であったウィリアム・オスラー先⽣にちなんでいると⾔われています。
要するにインターネット上で内科専攻医としての研修を登録して評価を受けるシステムのことです。皆さん、医療現場に出て実感していると思いますが、DX 化や効率化はまだまだ医療の世界では遅れています。地⽅のクリニックなどでは未だに FAX や紙カルテを運⽤しているところもあります。患者情報が読めない字で書かれた紹介状で送られてきて苛⽴った経験のある医師は僕だけではないでしょう。そんな医療界にあってオンラインでやり取りできる研修制度というのは、その点では先進的と⾔えるかもしれません。
しかしながら、J Osler をこなす内科専攻医の実態が、「3 時間机で勉強するよりも、ベッドサイドでの 15 分間が勝る」という名⾔を残したオスラー先⽣の意向とはかけ離れていることが問題です。皆さんも噂くらいは聞いたことがあるかもしれませんが、内科専攻医となって専⾨医を取得するためには(より正確には専⾨医試験を受験する資格を得るためには)、J Osler システムの下で症例登録と病歴要約と呼ばれる⼤量のレポートを提出しないといけません。2018 年に始まった J Osler 制度ですが、内科専⾨医以降のいわゆるサブスペ(循環器内科、腎臓内科など)の専⾨医を取得するためにも、それぞれの臓器別 JOsler が導⼊されてきています。
実際、どれくらい⼤変なのか?
そんな J Osler ですが、実際のところどれだけ⼤変なのでしょうか。
まず、J Osler では「症例登録」と「病歴要約」という 2 種類のレポートを作らないといけません。研修医の皆さんが仮に内科専攻医になるなら、症例登録は 120 症例、病歴要約は 29 症例作成するのが基本です。僕の場合は専攻医 2 年⽬の 10 ⽉ころから、1 年ほどかけて取り組むことになりました。当然、普段の臨床業務と並⾏しながらです。僕は J Oslerの進捗が遅かったので、⼀時期は午後の数時間を J Osler に専念するよう命じられたほどでした。規定の 3 年間で研修を終えることをあきらめて、「J Osler 留年」する⼈もいます。
症例登録では経験した症例の ID、性別、年齢などの患者情報を記⼊したうえで、「症例の概略」と「⾃⼰省察」を書いていきます。これを 120 症例です。病歴要約は A4 ⽤紙 2 枚分の分量で、29 症例を作成しないといけません。ここが J Oslerの難関であり、院内の指導医 3 ⼈と、「査読委員」と呼ばれる内科学会が任命した外部の評価委員をあわせて合計 4 回の評価を受けないといけません。
僕の場合、病歴要約ひとつを完成させて 4 回の評価を通過するまで、最低 10 時間はかかったと思います。29 症例では 300 時間近いです。当然、勤務終了後や休⽇に取り組むことが多いため、医局に 23 時近くまで残ってパソコンに向かうことも多かったです。
ただし、どれだけ時間がかかるかは所属施設や指導医に左右されることも多いです。病歴要約に相応の時間がかかるのは仕⽅ないのですが、その前段階の症例登録ではできるだけ時間をかけず、要領よく量を稼ぎたいところです。症例登録の記載字数については「1⾏でもいい」という内科学会のお墨付きもあります。患者情報を⼊⼒して、考察欄には軽く記載するだけで指導医が承認してくれればいいのですが、ここで丁寧な記載を要求されると途端に厳しい状況になります。症例登録については院内の 1 ⼈の指導医に承認してもらえばいいので、指導医の理解も重要です。
病歴要約でも指導医の⽅針が重要です。3 ⼈の指導医が関与することになりますが、それぞれどの程度、病歴要約の修正に関わるかは施設によりけりです。指導医の専⾨分野は評価が厳しかったりするので、そういうローカルな情報は⼊職後に仕⼊れましょう。⼀⽅で、外部の査読委員は誰になるかは運次第です。誤字脱字を⾒つけて修正してくれるだけの⼈から、内科学会のルールにはない独⾃⾒解で差替え(病歴要約を 1 つ無効にして新しく書き直しを命じること)してくる⼈、⾃分の専⾨分野にだけ異常に細かい考察を要求する⼈など様々です。運が悪いと、⾮常に多くの時間を J Osler に割かないといけないのが実情です。
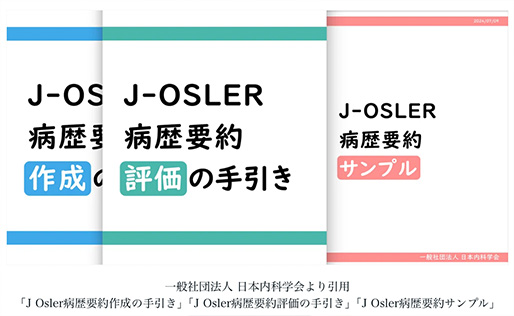
研修医のうちにやること
「J Osler を⾒据えて研修医のうちに何をすればいいか」とよく聞かれます。無料のオンライン相談を実施したときは、応募者の半数が研修医の先⽣だったほどです。正直、研修医のうちから J Osler のために何らかの準備をしている、あるいはしようとしている時点であなたは間違いなく J Osler など楽に突破できるでしょうというのが本⾳です。
研修医のうちにオンラインの J Osler システムにログインすることはできません。内科学会に⼊会し、内科専攻医として研修の始まる 4 ⽉にログインできるようになります。よって、専攻医になる前に症例登録や病歴要約は作ることができないんですね。
ただ、研修医のときに経験した症例を、内科専攻医になった後に J Osler に利⽤できるというルールがあります。症例登録 120 のうち 80 症例まで、病歴要約 29 のうち 14 症例までは研修医症例を利⽤できます。こういうルールがあるために、できるだけ研修医の間にJ Osler を進めれば後々有利になる、というアドバイスが時々聞かれます。
しかし個⼈的には、内科に進むと決めているとしても、研修医のときから準備するなら剖検症例など本当に貴重な症例の情報を保存しておくだけで⼗分であり、あとは初期研修の⽇々を楽しんで勉強し、無事に修了できれば⼗分かと思います。初期研修の症例を使⽤するとしても、内科専攻医レベルの考察を新たに書くことになるため、初期研修時代に書いた症例レポートをそのまま流⽤できることはありません。内科専攻医になってからの⽅が多くの症例を経験するはずなので、基本的には研修医の症例がなくても J Osler はクリアできる⼈が多いです。研修医の症例はあくまで補助程度です。
しかし、内科専攻医になってからのローテート次第では、研修医時代の症例に頼る⼈もいます。僕は、内科専攻医になってから総合内科で⻑く勉強させてもらったため、週 1 回の当直も含めると様々な症例を経験できたため、症例集めにはあまり苦労しませんでした。⼀⽅、⼤学の医局に⼊局するような場合は、専攻医になった後に専⾨科以外は回らない先⽣もいるようです。そういった場合は、初期研修症例が重要になる可能性もあるため、不⾜しそうな科の症例は保存しておきましょう。
剖検症例だけは初期研修のときから要注意
基本的に J Osler のために研修医のうちからやることなんてない、と⾔いましたが、剖検症例だけは例外です。内科専攻医になっても剖検症例に遭遇しない可能性もあるため、初期研修のうちに剖検症例を経験した場合、必ず情報を揃えておきましょう。患者さんの個⼈情報は削除したうえで、退院サマリーなど保存しておくのです。
というわけで、初期研修医のうちに J Osler を⾒据えるなら、剖検症例や勉強になった症例のデータを保存しておけば⼗分と思います。あとは健康に初期研修を全うできればいいのです
内科の魅⼒
ここまでの話しを聞くと、内科と他の診療科で迷っている⼈にとっては内科へのモチベーションが下がったかもしれません。いくら肯定的に表現しても、J Osler が多くの内科専攻医に負担になっているのは間違いない事実です。もちろん、医師になる⼈にはとんでもなく優秀で体⼒のある⼈がいるので、臨床もバリバリこなしながら J Osler を悠々攻略して、それでいて私⽣活も充実している、なんて⼈もいます。ただ、僕を含め多数派の⼈は苦労しています。J Osler の負担を理由に放射線科は⽪膚科など、他の診療科を選ぶ⼈もいるほどです。
それでも、内科にはそれなりの魅⼒があると思っています。外科系と違い⼿術はないので、1 ⼈⽴ちするまで⻑い間、指導医の下で教えてもらう必要はありません。ある患者さんから学んだ知識はそのまま次の患者さんに活かすことができます。「内科医はいらない」という病院やクリニックはありません。どこへ⾏っても需要があります。J Osler は事務作業ですが、逆に⾔えばなんの才能も要求されません。意外と⾃由に働きたい、⾃分のペースで⽣きたい⼈に内科が向いているのではないかと思っています。
まとめ(メッセージ)
最後まで読んでいただきありがとうございます。
研修医として⾊々な診療科をローテートしながら仕事を覚えるだけでも⼤変なのに、こうして専⾨研修以降も⾒すえて情報収集しているだけで⼤変にすごいことです。J Osler で課される症例登録と病歴要約が、多くの内科専攻医にとって負担であることは事実です。正直に⾔って、研修医から専攻医になると仕事の責任は倍増します。どの病院に進んでも、普段の臨床だけで⼗分に多忙でストレスに晒されることになるでしょう。そこに JOsler が加わります。そして、J Osler に必要な⽂書作成作業をこなした経験は、別に専⾨医取得後のスキルには役に⽴ちません。専⾨医を取得して 2 年経ちますが、改めてそう思います。
先⽣たちも、内科専攻医になればほぼ間違いなく J Osler を苦痛に感じる⽇が来ます。ハッキリ⾔って、J Osler は臨床とは別の事務処理能⼒を試すパソコン作業なのです。
それでも、この記事で述べたように内科には魅⼒があると思います。外科系診療科と違い、⾃分で学んで知識をつければそのままスキルになります。⼿技や⼿術を教わるために何年間も上司の⾔いなりになる必要はありません。また、需要と働く場所の多様さも内科医の魅⼒だと思っています。とりあえず内科専⾨医があれば、急性期病院だけでなくクリニック、訪問診療などいろいろな場所で働くことができます。内科医は必要としていない、という病院はないでしょう。そして、J Osler ⾃体は確かに⾯倒ですが、逆に⾔えば⾯倒なだけで特別な体⼒や才能を必要としません。時間さえあれば誰でもできる事務作業だからです。意外と⾃分のペースで⾃由な⼈⽣を歩みたい⼈に、内科はいい選択肢ではないでしょうか。もちろん、無理に内科を選ぶ必要はありませんが、J Osler を正しく理解して、興味がある⼈は恐れず内科を選んでほしいと思います。
残る研修⽣活が実り多いものとなることを願っています。

