医学生向け J-OSLER 「知らなきゃ損? 医学生のための内科入門」
2025 年 9 ⽉ 16 ⽇

⾃⼰紹介・あいさつ
はじめまして、相川よしたけと申します。こうして医学⽣向けに記事を書くのは初めての経験なので、⾃⼰紹介させていただきます。
僕は琉球⼤学医学部を卒業後、2020 年に福島県の病院で初期研修を終了し、内科専攻医となりました。「J Osler」という新しい内科専⾨研修プログラムを経て、2023 年に内科専⾨医となりました。その後は内科専⾨医として主にクリニックで勤務しています。現在、医師 7年⽬になります。
また、医師 5 年⽬のときに、⾃分と同じように J Osler に取り組む⼈たちのために X で発信を始めました。内科学会から公開される新しい資料などの情報も踏まえて、X や note、YouTube で発信を続けています。これまで多くの内科専攻医や研修医の相談に答えてきたこともあり、その界隈では⼀定の評価をいただいていると思います。
ちなみに、⼤学時代は極めて平凡というか特に取り柄のない学⽣だったと思います。部活は陸上競技部に⼊り、⻑期休みにはバックパッカーとしてアジアに貧乏旅⾏したり、他学部と⼀緒の英会話サークルに⼊ったり、たまに NPO 団体のボランティア活動に参加していました。⾃分なりに楽しい学⽣⽣活でしたが、試験のストレスが常につきまとっていいたため、学⽣時代、研修医、専攻医、そして今と徐々に⾃由で楽な⼈⽣になっていると感じます。つまり、学⽣時代が⼀番しんどかったです。この記事の本題からは逸れますが、これを読んでいる医学⽣の皆さんにも「⼈⽣は徐々に楽で⾃由になる」と思って楽に構えてほしいですね。
今回はそんな僕から、内科の魅⼒と、内科に進んだ後に待ち受ける「J Osler の現実」についてお話しします。研修医を終えた後に内科に進むと内科専攻医になるのですが、そこでは J Osler というプログラムのもとで多くのレポートを提出しなければなりません。
「J Osler って聞いたことがあるけど、良い評判を聞かない」
「まだ将来の診療科ははっきり決めていない」
「内科を選ぶとどんな医師⽣活になるのか想像できない」
まだまだ将来について未知の部分が多い医学⽣の皆さんにも、上記のような疑問に対して少しくらいはヒントを提⽰できるかと思います。この度、株式会社リンクスタッフ様より e-resident への記事執筆のご依頼をいただきました。医学⽣の皆さんに、内科の魅⼒やJ Osler についてお伝えしたいと思います。
J Osler とは
そもそも「J Osler」とは 2018 年に始まった内科専⾨研修プログラムのことです。⽇本内2科学会によると「内科専⾨研修の標準化を図るため、オンラインで研修実績の登録と評価ができるシステム」であり、Online system for Standardized Log of Evaluation andRegistration of specialty training System から名付けられたそうです(⽇本内科学会,https://www.naika.or.jp/nintei/j-osler/about/)。カナダの医師でジョン・ホプキンス⼤学の名物教授であったウィリアム・オスラー先⽣にちなんでいると⾔われています。皆さんが初期研修医を終えた後に内科を選ぶと内科専攻医となり、この J Osler に取り組むことになります。J Osler を通過すると内科専⾨医試験の受験資格を与えられ、これに合格すると内科専⾨医となれるというわけです。
2018 年に始まった J Osler 制度ですが、内科専⾨医になるための内科 J Osler の他にも、総合内科版 J Osler や、内科専⾨医以降のいわゆるサブスペ(循環器内科、腎臓内科など)を取得するための臓器別 J Osler も導⼊されています。内科系診療科を選ぶなら、JOsler は避けては通れないのが実際です。
J Osler ではインターネット上で内科専攻医としての研修を登録して評価を受けられるのですが、DX 化など効率化が遅れている医療界にあってオンラインでやり取りできる研修制度は、その点では先進的かもしれません。
内科 J Osler の実際
そんな J Osler ですが、実際のところ多くの内科専攻医の評判は悪いです。実際、僕のところに届いた悩みや不満の声は以下のようなものです。
・臨床で忙しくて J Osler のレポートを書く時間なんてない
・J Osler をこなすために毎⽇のように残業しているが、⾃⼰研鑽の扱いで残業代はない
・レポートを作ったが指導医がチェックしてくれない
・専⾨医取得後もこの病院に残らないなら J Osler の指導をしないと脅された
・専⾨外の医師から評価されるうちにレポートが劣化していく
・臨床能⼒ではなく、パソコンを使う事務作業に過ぎない
などなど⾊々あります。これらは僕⾃⾝が経験したり、またこれまで相談を受けてきたフォロワーが経験してきたものです。
J Osler では「症例登録」と「病歴要約」という 2 種類のレポートを作るのですが、症例登録は 120 症例、病歴要約は 29 症例を作成します。僕の場合は専攻医 2 年⽬の 10 ⽉ころから、1 年ほどかけて取り組みました。当然、普段の臨床業務と並⾏しながらでしたが、僕は J Osler の進捗が遅かったので、⼀時期は午後の数時間を J Osler に専念するよう命じられたほどでした。規定の 3 年間で研修を終えることをあきらめて、「J Osler 留年」する⼈もいます。
病歴要約ひとつにつき、院内の指導医 3 ⼈と外部の指導医 1 ⼈という、合計 4 回の評価を通過しないといけません。どれだけ時間がかかるかは所属施設や指導医に左右されるの3ですが、僕の場合、病歴要約 29 症例では 300 時間近くを要しました。当然、勤務終了後や休⽇に取り組むことが多いため、頻繁に医局に 23 時近くまで残ってパソコンに向かっていました。
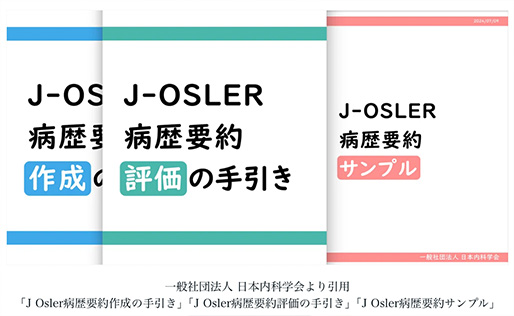
国家試験ほどのプレッシャーではない
そんな J Osler ですが、学⽣時代に経験した進級試験や医師国家試験ほどのプレッシャーはないというのが⼀般的です。すでに研修医も修了しているので⽣活は成り⽴ちますし、専⾨医を取得するのが 1 年遅れたとしても、その間は全く問題なく医師として働くことができます。「この 1 年は内視鏡(あるいは⼼臓カテーテル)の練習をしたいから、J Oslerは 1 年遅らせて来年取り組む」と割り切っている⼈もいました。さらに、別に専⾨医がなくても、医師として働く場所や機会は実はたくさんあります。むしろ急性期病院で専⾨医として働くより、専⾨医なしで働いている⼈のほうが時間もお⾦もゆとりがあったりします。
考え⽅は様々ですが、J Osler という専⾨研修プログラムで失敗したとしても、いくらでも⼈⽣をエンジョイできます。医学⽣の皆さんがいま経験している国家試験やテストの⽅が⼤変です。医師になってからも、学⽣時代の試験地獄が続くわけではないので、その点はご安⼼くださいね。
内科の魅⼒
ここまでの話しを聞いて内科に魅⼒を感じた⼈は多くないでしょう。実際、J Osler が多くの内科専攻医に負担になっているのは間違いない事実です。もちろん、医師になる⼈にはとんでもなく優秀で体⼒のある⼈がいるので、臨床もバリバリこなしながら J Osler を悠々攻略して、それでいて私⽣活も充実しているなんて⼈もいます。
それでも内科を勧めるなら、内科専⾨医を取得するのに特別な才能や体⼒が不要ということがあげられます。J Osler は事務作業ですが、逆に⾔えばなんの才能も要求されません。意外と⾃由に働きたい、⾃分のペースで⽣きたい⼈に意外と内科が向いているのではないかと思っています。
逆に内科を選ばないほうがいい⼈がいます。まずは、専⾨医取得のために臨床能⼒を正当に評価されたい⼈です。J Osler 制度では、とにかく病歴要約という⽂書作成が内科専⾨医取得のカギです。専⾨医に向けては書類作業のみが重視されます。臨床を熱⼼にやりすぎると専⾨医取得が遠ざかる可能性があるため、バリバリ臨床に取り組んで、その努⼒を正当に評価されたい⼈には向かないかもしれません。
次に、パソコン作業が嫌いな⼈も厳しいかもしれません。どんな診療科でも学会発表などのためにある程度はパソコン作業が要求されます。しかし、J Osler の佳境で求められる作業量はその⽐ではありません。医者ではなく会社の事務をやっている感覚です。そんな作業ができないと思ったら、内科専攻医はやめておきましょう。
最後に、⽂献を探したり、ガイドラインを読むのが嫌いな⼈には向いていないでしょう。これは J Osler というより、内科の適正になるかと思います。内科なので当然ではあるのですが、J Osler で病歴要約を作成するときも、考察に⽤いる⽂献を探す必要があります。ガイドラインを読む、その引⽤⽂献を調べる、UpToDate を使うなどの⽂献検索能⼒は必須です。こういったことができないと、J Osler どころではなくなります。
学⽣実習や研修医の間に、先⼊観を持たずに多くの診療科や医師たちを⾒て、⾃分の適正ややりがいを⾒つけてほしいと思います。
まとめ(メッセージ)
ここまで読んでいただきありがとうございます。僕は普段、医学⽣の⽅と接することはないのですが、想像するに僕が学⽣だったときよりも、今の医学⽣は多くの情報や噂に触れることができ、逆に不安になったり迷うことも多いような気がします。特に 2020 年のコロナ禍を契機として、世の中や医療を取り巻く状況は⼤きく変化しましたし、医師が選ぶキャリアも多様化しているのではないでしょうか。研修医を終えた後に美容医療に進む医師も増えているとのことです。
研修医の先⽣が選ぶ診療科としては、形成外科や泌尿器科、⽪膚科の⼈気が⾼まっていると思いますし、正直、内科の⼈気が⾼まっているとは⾔えないでしょう。近年の内科のイメージでいえば、この記事で述べた J Osler 以外にも、防護服を着たコロナの対応や⾼齢者の延命治療、他の診療科よりも多い当直などになるかもしれません。そうだとすると、決してプラスの印象ではないでしょう。内科よりも他の診療科が⼈気になるのも無理はありません。
もちろん、無理に内科を選ぶ必要はないのですが、J Osler や内科専攻医の⽣活を正しく知って専⾨研修を選んでほしいと思います。⼿前味噌にはなりますが、内科には魅⼒があると思っています。⾃分で学んだ知識がそのまま次の症例に役⽴つので、⾃分の成⻑を実感しやすい診療科です。外科系とは違い、⼿技や⼿術を教わるために何年間も上司の⾔いなりになる必要はありません。また、内科疾患に対応できれば、⼤体どんなクリニックや病院でも働くことができます。「内科医はいらない」という病院はありません。⾼齢社会の⽇本において、マルチプロブレムの患者への対応に関しては内科医がうまいことが多いです。例えば、訪問診療はどの診療科の医師でもできると思われがちですが、⾮常勤の他科の医師より、内科の医師のほうがうまくマネジメントできることが多いです。
そして、J Osler ⾃体は確かに⾯倒ですが、逆に⾔えば⾯倒なだけで特別な体⼒や才能を必要としません。時間さえあれば誰でもできる事務作業だからです。意外と⾃分のペースで⾃由な⼈⽣を歩みたい⼈に、内科はいい選択肢ではないでしょうか。
最後に、世の中がどうあろうと、学⽣の皆さんの貴重な⽇々の価値が落ちるわけではありません。部活やアルバイトに旅⾏に恋愛、いろいろなことにチャレンジして学⽣⽣活を楽しんでほしいと思います。いつか皆さんとお会いできる⽇を楽しみにしています。

