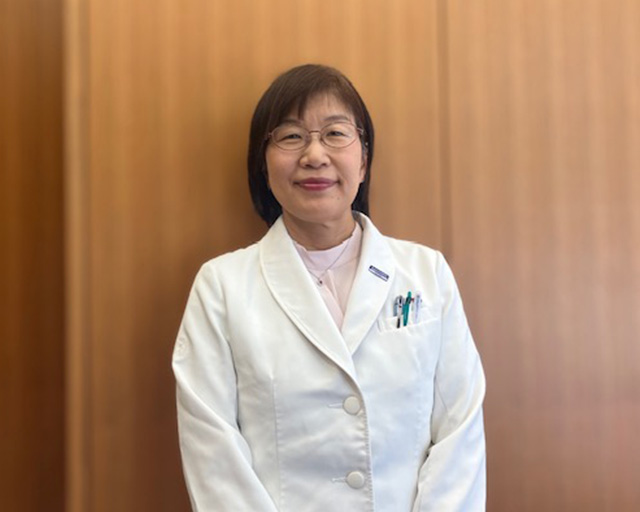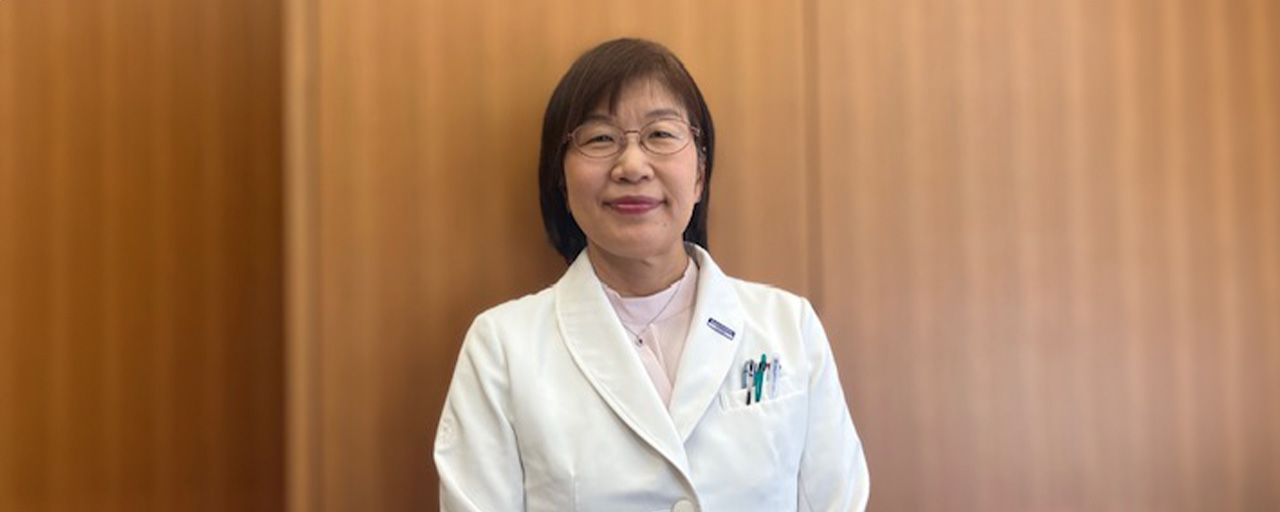【出演番組一部抜粋】
命を救う!スゴ腕ドクター・Nスタ・プロフェッショナル仕事の流儀・世界一受けたい授業
今回は【東京女子医科大学病院 乳腺外科教授】明石定子先生のインタビューです!
女性医師の外科医の苦労とは。どのようにして大学教授になったのか。
乳腺外科の今後についてなど語っていただきました― ―。
第2回「医師と患者で『綺麗』の感覚はやはり違うんです」をお話しいただきます。
目次
2. 医師を目指したきっかけをお聞かせください。
3. 東京大学を受験されたときは医師志望ではなかったのですね。
4. 理科II類からの医学部進学は難しいと聞きます。
5. 学生生活で思い出に残っていることはありますか。
6. 外科を選ばれたのも学生のときですよね。
7. 外科の中で第三外科を選ばれたのはどうしてですか。
8. 第三外科は女性が働きやすい医局だったのですね。
9. 外科に向いていると思われたのはどうしてですか。
10. 東京大学医学部附属病院での研修の日々はいかがでしたか。
11. その頃は乳腺外科ではなく、一般的な外科を診られていたのですよね。
12. 当時は胃がんが多かったのですか。
プロフィール
名 前:
病院名:
所 属:
資 格:
・日本乳癌学会乳腺専門医、指導医、理事
・検診マンモグラフィ読影認定医師
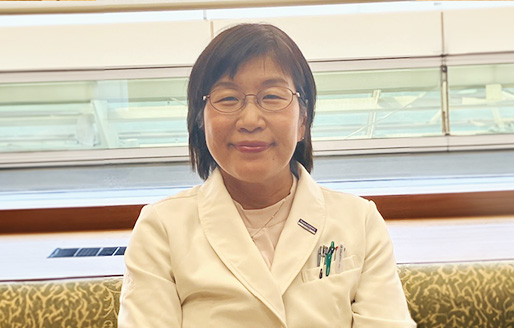
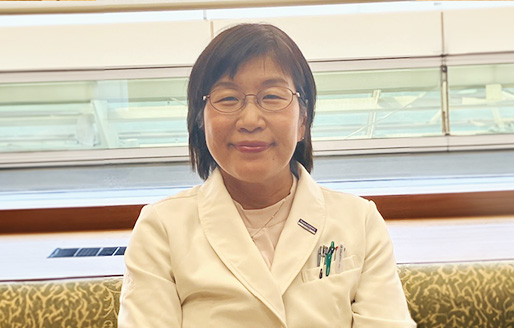
経 歴:
1990年3月(平成2年) 東京大学医学部医学科 卒業
1990年6月(平成2年) 東京大学医学部附属病院 第3外科 入局
1992年6月(平成4年) 国立がんセンター中央病院 外科レジデント
1995年6月(平成7年) 同 乳腺外科 がん専門修練医
1996年4月(平成8年) 国立がん研究センター中央病院 乳腺科 医員
2008年10月(平成20年) 同 16A病棟 医長/東京大学医学部 非常勤講師(兼任)
2011年10月(平成23年) 昭和大学医学部 外科学講座 乳腺外科学部門 准教授
2019年7月(令和元年) 同 教授
2022年9月(令和4年) 東京女子医科大学 外科学講座 乳腺外科学分野 教授・基幹分野長
■ 学位
医学博士(1999年4月28日/平成11年)
東京大学大学院 医学系研究科にて取得
■ 受賞歴
1999年 第5回 日本乳癌学会 研究奨励賞
2019年 国際ソロプチミスト日本財団 千嘉代子賞
■ 論文
英文論文:143編
和文論文:143編
■ 主な役職・活動歴
・厚生労働省
専門委員会 専門委員
・日本乳腺甲状腺超音波医学会
理事長/第40回学術集会 会長/第3回春季大会 大会長
・日本外科学会
代議員/保険診療委員/外科医労働環境改善委員
選挙管理・選挙制度検討委員/C-2水準審査委員会 委員
・日本臨床外科学会
評議員/編集委員会 副委員長/国内手術研修委員/広報委員
・日本乳癌学会
評議員/働き方検討委員会 副委員長
・日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会
理事/評議員/国際委員会 委員長/財務 副委員長
・JOHBOC
COI委員
・日本超音波医学会
代議員/国際交流委員会 委員
・日本女性外科医会
世話人(会計担当)
・JMA Journal
編集委員(乳腺分野)
・WFUMB2025
Local Organizing Committee
・NPO法人 日本女性技術者科学者ネットワーク
監事
・日本産婦人科乳腺医学会
理事(研修・認定担当)
━━ 国立がん研究センター中央病院でも研修されたのですね。
東大病院での研修後に、外科レジデントという立場でがんセンターに行きました。医局の先輩でがんセンターのレジデントになった方がいらっしゃったので、そういう道もあるんだなあと知ったのです。学生時代に大学病院以外で実習する機会があり、がんセンターで実習したことがあったのですが、そこで先生方の手術を見たことも大きかったです。がんセンターでは毎日、多くの手術をしているので、手術が上手な先生方ばかりなんですね。先生方の手術は速いし、動きに無駄がなく、こういうふうになりたい、ここで腕を磨きたいと思ったので、医局の教授に「がんセンターのレジデントになりたいです」とお願いしました。その教授は懐の深い方でしたので、「よしよし。しっかり勉強していらっしゃい」と送り出してくださいました。
━━ がんセンターでの修行の日々はいかがでしたか。
とにかく場数を踏まないとうまくならないと思っていましたし、実際に多くの手術を経験させていただきました。レジデント採用試験の前に説明会に出席しました。その説明会で記入する書類に外科の中で何を専門にしたいのかを書く欄がありました。当時のレジデントは卒後3年目から5年目の医師に応募資格があり、その説明会は2年目の秋にありましたので、まだ医師になって1年半しか経っていない時期だったのです。1年半のうち、最初の1年間は外科にいましたが、当時は1年目で執刀させて頂ける機会は数例しかなく、次の半年は麻酔科にいましたので、その状態で専門を決めろと言われてもまだ一人前の外科医にすらなっていないわけです。困ったなと考えた時に「そう言えば講師の先生が『明石くんは女性だから、将来は乳腺がいいんじゃない』と言ってくださってたな」と思い出したんです。それで何科かを書かないといけないのであれば、とりあえず乳腺にしようと決め、「乳腺」と書きました。そうしたら、乳腺外科の先生がとても喜んでくださいました。当時の外科はやはり消化器が主流の時代でしたので、私が乳腺を選んだことに対して、その先生は嬉しかったんでしょうね。その後もその先生にはとてもかわいがっていただきました。今日の自分があるのはその先生のお蔭だと感謝しています。
━━ 外科のレジデントを終えられてからは乳腺に特化されたのですか。
そうです。外科のレジデントとして胃、肝胆膵、大腸、肺、乳腺など各臓器別の癌手術のトレーニングを3年間受け、そのあと乳腺外科のチーフレジデントになりました。そこからは完全に乳腺のみですね。当時としては消化器外科を何年か経験してから乳腺に行く先生方が多かったのですが、私の場合は早い時期に専門特化したので、それが強みでもあるし、弱みでもあるのかなと思っています。
━━ 弱みでもあるのですか。
やはり乳がん以外のことに少し弱いという自覚があります。乳腺に行く前にもう少し色々なことを知っておいたほうが良かったのかなという思いもありましたが、人間は欲を言うとキリがないですしね。

━━ 乳腺に特化されてからの修練の日々はいかがでしたか。
お蔭様で、非常に楽しかったです。がんセンターは症例数が非常に多いので、自分の腕を磨くという意味でも良い機会でした。論文も書き放題でしたね(笑)。論文も最初は何を書いていいのか分からないので、「ネタをください」と上の先生方にお願いをしていましたが、途中からは自分で「これはどういうことなんだろう」という疑問を持てるようになってきました。症例数が豊富にあるので、臨床上で疑問に思ったことを研究し、論文に書いていくということを繰り返しながら、楽しい日々を過ごしていました。
━━ 手術をどのように上達させていったのですか。
人の手術を見ているだけでうまくなる人もいるかもしれませんが、やはり自分が執刀してみることで、「ここが難しい」などが分かってきます。そのため、ある程度の腕になるまでは術者の立場をもらわないとうまくならないのではないかと思います。私は幸い、がんセンターで術者になる機会に恵まれたというのが有り難かったですね。機会に恵まれただけでなく、仲間の存在もあります。がんセンターのレジデントは皆、手術がうまくなりたくて、がんセンターを選んでいます。それで、がんセンターの安月給にもあえて耐えているわけなので(笑)、「この症例は自分のところに来ないかなあ」という感じで、皆ががつがつしていました。そこはチーフレジデントが均等になるように配慮して、うまく回していましたが、そういう環境の中で上達させていきました。(大胸筋膜を残すことは研究会での他院の先生が病床が足りなかった時にドレーンが早く抜ける技として発表されていたものを取り入れたところ、痛みが軽減していることに気づいた経緯で始めたものです)
━━ 患者さんとどのようにコミュニケーションを取られるのですか。
乳がんの患者さんは増えており、様々なニーズがありますが、中でも乳房の整容性へのニーズは大きいですね。医師が考える「綺麗」と患者さんが考える「綺麗」はやはり違います。そこで、患者さんの立場に立って、患者さんの思いを汲み取ることに努力してきました。温存療法が始まった頃に、私としては綺麗に整えたと思った手術をしたのですが、その後、患者さんが脂肪注入をされ、乳房の形を整え直されたというお話を耳にしました。そのときに乳房への思い入れは皆さんが違うのだということを感じましたし、一方で、患者さんの年齢や組織の状態などでも「綺麗」のあり方は変わってきます。そうした現実は患者さんにきちんと伝えるようにしています。しこりの大きさや場所を考え、切除する範囲や切除する量を決めていくのですが、乳房の形がどう変形するのかについては患者さんの求めるイメージと予測されるイメージとのギャップを埋めなくてはいけません。このコミュニケーションはとても大事だと思っています。
━━ 乳がん診療は手術だけではありませんよね。
薬物療法もありますね。こちらも患者さんのニーズは様々です。異型度が高く、抗がん剤が必要な患者さんでも副作用などが気になって拒否される方もいます。もちろん、抗がん剤には副作用が全くないわけではありません。でも、今は吐き気止めなどの薬も進化していますし、抗がん剤治療を受けた患者さんの中にも「想像していたよりも辛くなかった」と言われる方が少なくありません。私も患者さんの多様なニーズにお応えするために、遺伝子分析や術前術後の薬物療法についての臨床研究に力を入れてきました。